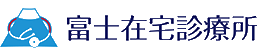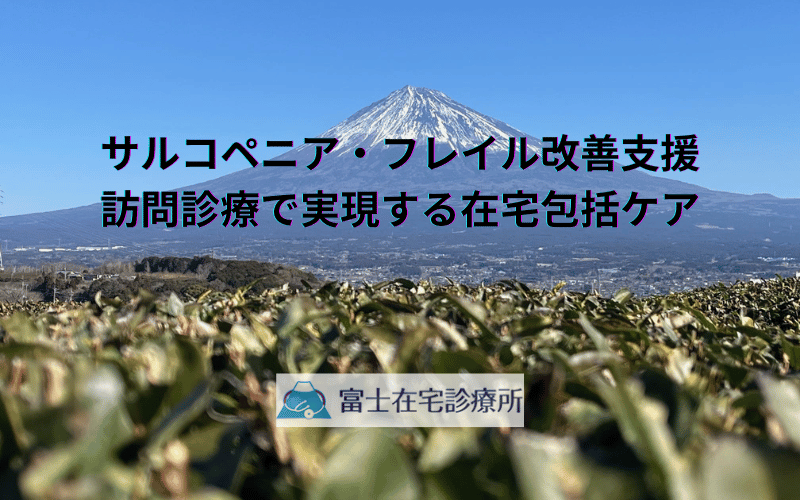訪問リハビリは週何回が効果的?要介護度別の頻度目安と費用の違い
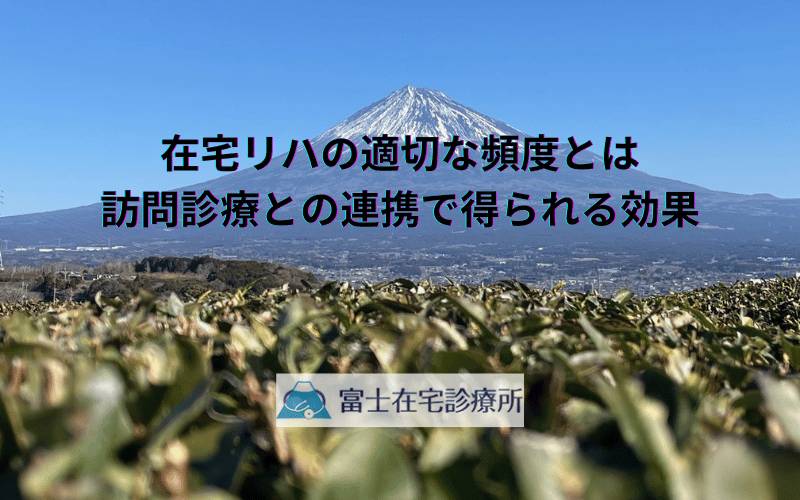
在宅でのリハビリテーションを検討する際、「どのくらいの頻度で行えば効果が出るのか」は多くの方が悩む点です。
ご自宅という安心できる環境でリハビリを行うことは、機能の維持・回復に大きな意味を持ちます。しかし、やみくもに回数を増やせば良いというものでもありません。
患者さんお一人おひとりの状態や目標、生活環境に合わせて適切な頻度を設定することが重要です。
この記事では、在宅リハビリテーションの基本的な知識から、適切な頻度を決定するための要素、そして訪問診療と連携することによって得られる具体的な効果について、詳しく解説していきます。
在宅リハビリテーションの基本と訪問診療との連携
ご自宅で受けるリハビリテーションには、病院とは異なる特徴があります。
ここでは、在宅リハビリテーションがどのようなものか、また、訪問診療や訪問看護といった他の在宅サービスとどのように連携し、役割を分担しているのか、基本的な点を解説します。
在宅リハビリテーションとは何か
在宅リハビリテーションとは、病気や怪我、加齢などによって心身の機能が低下した方に対して、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門職(セラピスト)が直接ご自宅を訪問し、リハビリを行うサービスです。
病院や施設でのリハビリと大きく異なる点は、「実際の生活の場」で行うことです。
病院では行わなかった「玄関の段差を上がる」「自宅のトイレで動作する」「台所で調理する」といった、より具体的で実践的な訓練を行います。
これにより、患者さんがご自宅でより安全に、その人らしい生活を送れるように支援します。
単に筋力や関節の動きを改善するだけでなく、日常生活動作(ADL)の自立度を高め、生活の質(QOL)を維持・向上させることが大きな目的です。
また、ご家族に対して介助方法の指導を行ったり、福祉用具の選定や住宅改修のアドバイスを行ったりすることも重要な役割の一つです。
在宅リハビリを担う主な専門職
- 理学療法士(PT)
- 作業療法士(OT)
- 言語聴覚士(ST)
理学療法士は、起き上がる、座る、立つ、歩くといった基本的な動作能力の回復を目指します。
作業療法士は、食事、着替え、入浴、家事といった日常生活の応用的な動作や、趣味活動など、その人らしい生活を送るためのリハビリを行います。
言語聴覚士は、話す、聞くといった意思疎通の課題や、食べる、飲み込むといった嚥下(えんげ)機能の課題に対応します。これらの専門職が、患者さんの状態に合わせて関わります。
訪問診療・訪問看護との役割分担
在宅での療養生活は、多くの場合、リハビリ専門職だけでなく、医師、看護師など複数の職種がチームとなって支えます。
特に訪問診療は、通院が困難な患者さんのご自宅へ医師が定期的に訪問し、診察、治療、薬の処方、健康管理などを行う医療サービスであり、在宅リハビリと密接に関連します。
訪問看護は、看護師がご自宅を訪問し、医師の指示に基づき点滴や褥瘡(じょくそう)の処置、体調管理、医療機器の管理などを行います。
在宅リハビリは、これらの医療サービスと連携し、医学的な管理のもとで安全に機能訓練を進める役割を担います。
それぞれの専門性を生かしながら情報を共有し、一体となって患者さんの生活を支えます。
在宅サービスの役割分担
| サービス名 | 主な役割 | 関わる職種 |
|---|---|---|
| 訪問診療 | 医学的管理、診断、治療、健康管理全般 | 医師、看護師 |
| 訪問看護 | 医療的ケア(点滴・処置)、健康状態の観察、療養相談 | 看護師、准看護師、保健師 |
| 在宅リハビリ | 機能訓練、日常生活動作訓練、環境調整、介助指導 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
在宅リハの対象となる患者の特徴
在宅リハビリテーションは、主に通院してリハビリを受けることが困難な方を対象としています。
例えば、脳梗塞や脳出血の後遺症で歩行が難しい方、パーキンソン病などの神経難病が進行している方、骨折後の手術で体力が低下した高齢の方、長期間の入院で筋力が落ちてしまった「廃用症候群」の方などです。
また、退院直後でご自宅での生活に不安がある方や、ご家族が介助方法に悩んでいる場合も対象となります。
ご自宅での生活動作(トイレ、入浴、移動など)に具体的な課題があり、専門的な指導や訓練が必要と医師が判断した場合に、在宅リハビリが導入されます。
在宅リハビリの主な対象となる状態
| 分類 | 具体的な疾患・状態 | リハビリの主な目的 |
|---|---|---|
| 脳血管疾患 | 脳梗塞・脳出血後遺症、くも膜下出血後 | 麻痺の改善、歩行訓練、日常生活動作の再獲得 |
| 運動器疾患 | 大腿骨頚部骨折後、変形性関節症、脊柱管狭窄症 | 筋力強化、関節可動域訓練、痛みの緩和、歩行安定 |
| 神経難病 | パーキンソン病、ALS、脊髄小脳変性症 | 進行抑制、拘縮予防、呼吸リハ、嚥下訓練 |
| 廃用症候群 | 長期臥床による全身の体力・筋力低下 | 早期離床、起き上がり、座位保持、筋力維持・向上 |
| 呼吸器・循環器 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD)、心不全 | 呼吸訓練、持久力向上、活動量の調整 |
病院リハビリから在宅リハへの移行
入院中から退院後の生活を見据え、病院のスタッフと在宅サービスのスタッフが連携することが非常に重要です。
多くの病院では、退院が近づくと「退院前カンファレンス」を開き、患者さんご本人、ご家族、病院の医師・看護師・リハビリ担当者、そして退院後に関わる在宅医、訪問看護師、ケアマネジャー、在宅リハビリ担当者などが集まります。
この場で、患者さんの状態や病院でのリハビリ内容、退院後の生活で想定される課題などを共有します。
これにより、退院後すぐに、病院でのリハビリ内容を引き継いだ、切れ目のない在宅リハビリを開始できます。
在宅のスタッフが事前に入院中の様子を把握し、ご自宅の環境を確認しておくことで、よりスムーズな移行が実現します。
在宅リハの頻度を決定する要素
在宅リハビリの頻度は、一律に決まるものではありません。患者さんの状態や目標、そしてご家族の状況など、多くの情報を総合的に評価して決定します。
ここでは、頻度を決定する際に考慮すべき主要な要素について解説します。
患者の身体機能と疾患の状態
リハビリの頻度を決定する上で最も重要な要素は、患者さんご自身の身体機能と、疾患がどの時期(ステージ)にあるかです。
例えば、脳梗塞や骨折の治療直後(急性期)を過ぎ、機能回復が最も期待できる「回復期」にあたる場合は、集中的なリハビリが効果的であるため、頻度を多めに(例えば週2~3回以上)設定することがあります。
一方、病状が安定し、現在の身体機能を維持することが主な目的となる「維持期」では、週1~2回程度の頻度で状態をチェックしながら、ご自宅での自主トレーニングと組み合わせて進めることが一般的です。
また、終末期(ターミナル期)の患者さんに対しては、苦痛の緩和や安楽な姿勢の保持、ご家族への介助指導などを目的として、状態に合わせて頻度を設定します。
病状の時期とリハビリ頻度の目安
| 病状の時期 | 主な状態 | 頻度の目安(例) |
|---|---|---|
| 回復期(在宅) | 退院直後、機能改善が期待できる時期 | 週2~3回以上 |
| 維持期 | 病状が安定し、機能が比較的安定している時期 | 週1~2回 |
| 終末期 | QOL維持、苦痛緩和、安楽な体位の保持 | 必要に応じて(週1回など) |
医学的管理の必要性と介入レベル
心不全、呼吸器疾患、重度の糖尿病、コントロールが難しい高血圧など、基礎疾患の状態によっては、リハビリの負荷量が体調に大きく影響することがあります。
このような場合、訪問診療医による綿密な医学的管理のもとで、安全に配慮しながらリハビリを進める必要があります。
医師が患者さんの全身状態を常に把握し、「今どの程度の負荷までなら安全か」を判断します。この医師の評価に基づき、リハビリの頻度や一回あたりの時間を調整します。
体調が不安定な時期は頻度を減らしたり、逆に安定して改善が見込める時期には医師の許可のもとで頻度を増やしたりと、柔軟な対応が求められます。
介護保険と医療保険の適用範囲
在宅リハビリテーションは、「介護保険」または「医療保険」のどちらかを利用して行います。どちらの保険が適用されるかは、患者さんの年齢や疾患、状態によって決まります。
65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方は、原則として介護保険の「訪問リハビリテーション」を利用します。
この場合、ケアマネジャーが作成するケアプランの範囲内で、他の介護サービスとのバランスを考えながら頻度が決まります。
一方、厚生労働大臣が定める特定の疾患(パーキンソン病やALSなどの難病、末期がんなど)の方や、急性増悪などで医師が集中的なリハビリが必要と判断した場合は、医療保険が適用されます。
医療保険の場合、利用できる日数や回数に介護保険とは異なる定め(例:疾患によっては週6回まで可能など)があり、より集中的な介入が可能な場合があります。
ご自身がどちらに該当するかは、主治医やケアマネジャーに確認することが重要です。原則として、両方の保険を同時に利用することはできません。
介護保険と医療保険のリハビリ比較
| 項目 | 介護保険(訪問リハビリ) | 医療保険(在宅患者訪問リハビリ指導料など) |
|---|---|---|
| 主な対象 | 要介護・要支援認定を受けている方 | 厚生労働大臣が定める疾患の方、急性増悪時など |
| 利用限度 | ケアプランの支給限度額の範囲内 | 疾患や状態に応じた日数制限(例:週6回) |
| 窓口負担 | 原則1割~3割負担 | 原則1割~3割負担(年齢・所得による) |
ご家族の介護力と生活環境
患者さんを支えるご家族の介護力や、介護に割ける時間も、リハビリの頻度や内容を考える上で重要な要素です。
例えば、日中お一人で過ごす時間が長い患者さんの場合、リハビリ専門職が訪問する回数を増やすことで、安全確認や体調変化の早期発見につながることがあります。
また、ご家族が介助方法に不安を抱えている場合は、リハビリの頻度を一時的に増やし、介助指導を集中的に行うこともあります。
ご家族が介助のコツを掴むことで、患者さんご本人も安心して動作できるようになり、結果としてリハビリ効果が高まることも少なくありません。
さらに、ご自宅の環境(手すりの有無、段差、動線など)も評価し、環境調整のアドバイスと訓練を並行して行うため、これらの課題が多い場合は頻度を調整することがあります。
リハビリの目標設定と期間
「なぜリハビリを行うのか」という目標を明確にすることが、適切な頻度設定につながります。
患者さんご本人やご家族が「何をしたいか」「どうなりたいか」を、リハビリ担当者や医師と共有し、現実的で具体的な目標を設定します。
例えば、「3ヶ月後までに、杖を使って自宅のトイレまで一人で行けるようになる」といった目標です。
この目標を達成するために必要な訓練量や期間を予測し、そこから逆算して「それなら週2回は集中的に訓練しましょう」といった形で頻度を決定します。
目標が達成されれば、次の新たな目標を設定したり、頻度を減らして維持期に移行したりします。目標が明確であることは、患者さんのリハビリへの意欲(モチベーション)を保つ上でも非常に大切です。
目標設定の例
- 短期目標(例: 3ヶ月以内に、手すりを使って5m歩ける)
- 長期目標(例: 6ヶ月以内に、介助なしで自宅内トイレに行ける)
頻度別にみる在宅リハの効果と実践例
リハビリの頻度によって、期待できる効果やアプローチの方法が異なります。
ここでは、週1回、週2回、週3回以上といった頻度別に、どのような目的で実施され、どのような効果が期待できるのかを具体的に解説します。
週1回実施の場合 維持期における効果
週1回の在宅リハビリは、主に病状や身体機能が比較的安定している「維持期」の患者さんに行われることが多いです。
この頻度での主な目的は、現在の身体機能や日常生活動作の能力を「維持」すること、そして「低下させない」ことです。
高齢の方や慢性疾患を持つ方は、何もしないと徐々に筋力や体力が落ちてしまいがちです。
週に1回、専門職が訪問し、関節が硬くなる(拘縮)のを防ぐストレッチや、筋力維持のための軽い運動、バランス訓練などを行います。
また、この訪問機会を利用して、患者さんの体調や生活状況に変化がないかを定期的にチェックします。
ご家族へ介助方法の再確認や指導を行ったり、ご自宅で安全に行える自主トレーニングの内容を見直したりする場としても重要です。
効果を持続させるためには、リハビリ専門職が訪問しない日に、ご自身やご家族で自主トレーニングを継続することが大切です。
週2回実施の場合 改善期の標準的アプローチ
週2回の頻度は、在宅リハビリにおいて最も多く見られる標準的なアプローチの一つです。
特に、退院直後や、病状が安定してきて「これから機能回復を目指したい」という「改善期」の患者さんに適しています。
週1回の介入では、訓練の効果が定着する前に次の訪問日になってしまうことがありますが、週2回(例えば月曜日と木曜日など)行うことで、訓練と定着のサイクルを効果的に回すことができます。
1回目の訪問で集中的に筋力強化や動作訓練を行い、2回目の訪問でその動作が日常生活の中で実際にできているかを確認し、課題を修正するといった進め方が可能です。
このペースで継続することで、患者さんご自身も「先週より楽に立てるようになった」「少し長く歩けるようになった」といった効果を実感しやすく、リハビリへの意欲向上にもつながります。
訪問診療医や看護師とも連携し、体調の変化を見ながら訓練内容を調整しやすい頻度でもあります。
週2回のリハビリ内容例(脳梗塞後遺症・軽度麻痺)
| 介入日 | 1回目(例: 月曜) | 2回目(例: 木曜) |
|---|---|---|
| 主な内容 | 麻痺側の筋力増強訓練、関節可動域訓練、基本動作訓練(寝返り・起き上がり) | 立位・歩行訓練(装具や杖の使用)、日常生活動作訓練(トイレ動作・更衣)、自主トレ指導 |
| 目的 | 身体機能の基礎的な改善、動作の土台作り | 実生活への応用、動作の定着、家族への介助指導 |
週3回以上実施の場合 集中的介入が必要なケース
週3回以上の頻回なリハビリは、特に集中的な介入が必要と判断された場合に行います。例えば、急性期病院を退院した直後で、廃用症候群の予防と早期の機能回復が強く望まれる時期です。
この時期に集中的に介入することで、寝たきりになるのを防ぎ、早期に離床や座位、立位へとつなげていく効果が期待できます。
また、食べ物や飲み物の飲み込みが難しくなる「嚥下障害」が重度で、誤嚥性肺炎のリスクが非常に高い患者さんに対し、言語聴覚士が集中的な嚥下訓練を行う場合もあります。
その他、パーキンソン病などの進行性の神経難病で、医療保険が適用される場合も、週3回以上のリハビリが行われることがあります。
この頻度での介入は、患者さんの体力的な負担も考慮する必要があるため、訪問診療医による厳密な医学的管理のもとで、その日の体調を慎重に見極めながら実施します。
集中的介入が検討される状態の例
| 対象の状態 | リハビリの焦点 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 急性増悪後の退院直後 | 早期離床、基本動作(起き上がり・座位)の再獲得 | 廃用症候群の予防、早期の日常生活自立 |
| 嚥下障害(重度) | 摂食・嚥下機能の集中訓練、食事形態の評価 | 誤嚥性肺炎の予防、安全な経口摂取の維持・再開 |
| 神経難病(医療保険適用) | 拘縮予防、呼吸機能の維持、QOLの維持 | 症状進行の緩和、苦痛緩和、介助負担の軽減 |
訪問診療との連携がもたらす相乗効果
在宅リハビリテーションの効果を高める上で、訪問診療を行う医師との連携は非常に重要です。
医学的な視点を持つ医師と、生活の視点を持つリハビリ専門職が情報を共有することで、より安全で質の高いケアが実現します。
この連携が、リハビリの頻度設定や内容の調整にも大きく寄与します。
医学的評価に基づくリハビリ計画の最適化
在宅リハビリを行う患者さんは、多くの場合、複数の基礎疾患(高血圧、心疾患、糖尿病など)を抱えています。リハビリ専門職は動作の専門家ですが、医学的な最終判断はできません。
訪問診療医が主治医として患者さんの全身状態、血液データ、服薬状況などを正確に把握し、「現在の状態で、どの程度のリハビリ負荷が適切か」「リハビリを行う上での禁忌事項(やってはいけないこと)はないか」を医学的に評価します。
この医師の評価と指示に基づき、リハビリ専門職は安全な範囲内で最大限の効果を目指すリハビリ計画を作成します。
医師の医学的根拠と、療法士の生活機能評価が組み合わさることで、計画がより精度の高いものになります。
定期的な情報共有による効果的な頻度調整
患者さんの体調は一定ではありません。特に在宅療養中は、天候や日常の出来事によっても体調が変動しやすいものです。
リハビリ専門職は、週に数回、患者さんと直接接するため、その日の血圧や脈拍、表情、会話の様子、皮膚の状態など、細かな変化に気づきやすい立場にあります。
例えば、「最近、リハビリ中の息切れが強い」「足のむくみが先週より悪化している」といった情報を、すぐに訪問診療医に報告します。
医師はその情報を受け、必要であれば訪問して診察したり、薬の調整を行ったりします。
そして、「今週はリハビリの頻度を週2回から1回に減らして様子を見ましょう」「負荷量を少し下げてください」といった具体的な指示を出します。
この迅速な情報共有により、体調悪化を未然に防ぎつつ、常に患者さんの状態に合った効果的な頻度での介入が可能になります。
医師と療法士の情報共有の例
| 共有する情報 | 医師の対応(例) | リハビリへの反映(例) |
|---|---|---|
| 療法士「リハビリ中に血圧が異常に上昇」 | 医師「降圧薬の調整、塩分摂取状況の確認」 | リハビリ前に必ず血圧測定、高値時は中止を検討 |
| 医師「肺炎の兆候あり、抗生剤開始」 | 医師「安静指示、水分摂取の励行」 | リハビリ一時休止、または呼吸リハのみに変更 |
| 療法士「転倒したが外傷なし。歩行不安定」 | 医師「往診し骨折等の有無確認」 | 歩行訓練を見直し、手すり設置などを再検討 |
急変時の迅速な対応と安全管理
在宅リハビリを行う上で最も配慮すべきことの一つが、リハビリ中の体調急変です。
万が一、リハビリ中に患者さんの意識状態が悪くなったり、強い胸痛を訴えたりした場合、訪問診療医と連携体制が整っていれば、リハビリ担当者は応急処置を行いながら、すぐに主治医である訪問診療医に電話で連絡します。
医師は状況を聞き、リハビリ担当者に対応を指示するとともに、緊急で往診を行ったり、救急搬送の手配をしたりします。
主治医が日頃の状態を把握しているため、救急隊や搬送先病院への情報提供もスムーズです。
「何かあっても、すぐに医師に連絡が取れる」という安心感が、患者さんご本人、ご家族、そしてリハビリ担当者にとっても、在宅でリハビリを安全に進めるための大きな支えとなります。
多職種チームによる包括的なケアの実現
在宅療養は、医師とリハビリ専門職だけで完結するものではありません。訪問看護師、ケアマネジャー、薬剤師、ホームヘルパー、福祉用具の専門相談員など、非常に多くの職種が関わります。
訪問診療医は、これらの多職種チームの中心的な役割を担い、患者さんの医学的な情報を集約し、治療やケアの全体的な方針を決定します。
例えば、リハビリで「歩行が安定してきた」という情報があれば、医師は「転倒のリスクが減ったか」を評価し、看護師は「入浴介助の方法を変えられるか」を検討し、ケアマネジャーは「デイサービスの利用を増やせるか」を計画します。
このように、リハビリの効果を生活全体の質の向上につなげるために、訪問診療医を中心としたチームアプローチが大きな力を発揮します。
在宅チームの構成メンバー例
- 医師(訪問診療)
- 看護師(訪問看護)
- リハビリ専門職(PT・OT・ST)
- ケアマネジャー(居宅介護支援)
- 薬剤師(在宅訪問)
- ホームヘルパー(訪問介護)
効果を最大化するための頻度管理のポイント
設定された頻度でリハビリを行うだけでなく、その効果を最大限に引き出すためにはいくつかの工夫が必要です。
定期的な評価の見直しや、ご家族の協力、他のサービスとの連携など、頻度管理と合わせて考えたいポイントを解説します。
定期的な効果測定と頻度の見直し
在宅リハビリを開始する際、「リハビリテーション計画書」というものを作成します。これには、患者さんの状態、リハビリの目標、具体的な訓練内容、そして頻度が記載されます。
計画は立てたままにするのではなく、定期的に(例えば3ヶ月ごとや6ヶ月ごと)見直しを行うことが重要です。
リハビリ担当者が、筋力、関節の可動域、歩行速度、日常生活動作の自立度などを客観的に測定し、効果が出ているかを評価します。
もし目標が達成されていれば、次の新たな目標を設定します。
もし効果が十分でない場合は、その原因(頻度が足りないのか、内容が合っていないのか、体調の変化があったのか)を分析し、訪問診療医とも相談の上で、頻度や訓練内容の変更を検討します。
この見直しにより、常に効果的なリハビリを継続できます。
ご家族が取り組む自主トレーニングとの組み合わせ
リハビリの効果を上げるためには、専門職が訪問する週に数回、数十分の時間だけでは不十分な場合が多いです。
大切なのは、リハビリで獲得した動きや体力を、日常生活の中で維持・向上させていくことです。
そのために、リハビリ担当者は、患者さんがご自宅で一人でも安全に行える、またはご家族が少し介助すれば行える「自主トレーニング」を指導します。
例えば、ベッドの上でできる簡単な足の運動、椅子を使った立ち座りの練習などです。
ご家族には、これらの運動を日々の生活の中で行うよう声かけをしたり、安全に見守ったりといった役割をお願いすることがあります。
リハビリのない日にも自主トレーニングを組み合わせることで、週1~2回の頻度でも高い効果を維持することが期待できます。
自主トレーニングの例と家族の役割
| 目的 | 自主トレの例 | 家族の役割 |
|---|---|---|
| 筋力維持 | ベッド上での足首や膝の曲げ伸ばし | 実施したかの確認、回数を一緒に数える |
| 関節拘縮予防 | ご自身での簡単なストレッチ | 安全な範囲での介助、痛みの有無の確認 |
| バランス訓練 | 椅子につかまっての立位保持訓練 | 転倒しないよう必ず側で見守る、時間を計る |
介護施設や通所サービスとの併用
在宅リハビリと並行して、デイケア(通所リハビリテーション)やデイサービス(通所介護)といった通いのサービスを利用することも、効果を高める上で有効な場合があります。
デイケアでは、施設にリハビリ専門職が常駐しており、専用の機器を使った訓練や集団での体操などを行います。
デイサービスでは、他者との交流やレクリエーションが中心となりますが、これが良い社会的刺激となり、心身の活性化につながることもあります。
ただし、サービスを詰め込みすぎると、かえって患者さんの疲労につながることもあります。
「在宅リハでは自宅での動作を集中的に行い、デイケアでは機器を使った筋力訓練を行う」といったように、それぞれのサービスの役割を明確にすることが重要です。
ケアマネジャーや訪問診療医とよく相談し、患者さんの体力や目標に合った最適なサービスの組み合わせと頻度を見つけることが求められます。
モチベーション維持と継続のための工夫
リハビリは、効果が出るまでに時間がかかることもあり、時には単調に感じることもあるかもしれません。特にご自宅でのリハビリは、他者の目がない分、意欲の維持が難しい側面もあります。
リハビリの効果を最大化するには、患者さんご本人が「良くなりたい」「続けたい」と思う意欲が何よりも大切です。
リハビリ担当者は、単に訓練を行うだけでなく、患者さんの趣味や興味(例えば「庭の花を見に歩きたい」「もう一度編み物がしたい」など)をリハビリ内容に取り入れたり、小さな「できた」という成功体験をご本人やご家族と共有したりする工夫をします。
また、訪問診療医や訪問看護師が、リハビリの成果を医学的な視点から評価し、「血圧が安定してきたのは、リハビリで体力がついた効果もありますね」といった励ましの言葉をかけることも、継続のための大きな支えとなります。
意欲を引き出す工夫
- 「孫と散歩する」など具体的な生活目標の共有
- 趣味活動(園芸、料理、書道など)の動作を訓練に取り入れる
- ご家族や医師・看護師からの積極的な励ましと賞賛
おしまいに
在宅リハビリテーションというと、「歩けるようになること」や「自分の力で動けるようになること」だけが目的だと思われがちです。しかし、私たちが考えるリハビリの価値は、それだけではありません。
例えば、ベッドで過ごす時間が長い方の場合、何もしないと股関節が徐々に固くなり、おむつ交換で足を開くたびに強い痛みを感じるようになってしまいます。 リハビリ専門職が関わり、関節の柔軟性を保つケアを行うことは、こうした「日々の介助に伴う痛み」を取り除き、患者さんが穏やかな時間を過ごせるようにするために非常に重要です。これもまた、大切なQOL(生活の質)の向上だと私たちは考えています。
当院では、機能の回復を目指す方はもちろん、現在の機能を維持し、苦痛なく自分らしい生活を続けていただくために、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)による訪問リハビリを積極的にご提案しています。
「こんな状態でもリハビリをして意味があるのかな?」と迷われている場合も、ぜひ一度私たちにご相談ください。その方に合わせた、最適なリハビリの形を一緒に考えていきましょう。
在宅リハに関するよくある質問
最後に、在宅リハビリテーションの頻度や効果に関して、多くの方から寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 在宅リハビリはどのくらいの期間続ければ効果が出ますか?
-
効果を実感できるまでの期間は、患者さんの状態や疾患、リハビリの目標によって大きく異なります。
例えば、骨折後のリハビリであれば数ヶ月で目に見える効果(歩行の安定など)が出ることが多いです。
一方で、パーキンソン病などの神経難病のように、機能の維持や低下の予防を目指す場合は、長期的な継続そのものが効果であるとも言えます。
大切なのは、短期的な目標(例:1ヶ月後)と長期的な目標(例:半年後)を設定し、定期的に達成度を確認しながら続けることです。
訪問診療医やリハビリ担当者と相談しながら、焦らずご自身のペースで取り組むことが重要です。
- 訪問診療と訪問リハビリは必ずセットで利用するものですか?
-
必ずしもセットで利用しなければならない訳ではありません。かかりつけのクリニックに通院しながら、訪問リハビリテーションのみを利用することも制度上は可能です。
しかし、在宅でリハビリを必要とされる患者さんは、何らかの医学的管理を通院ではなくご自宅で必要としているケースがほとんどです。
訪問リハビリテーションは医師の指示に基づいて行われます。
訪問診療医が患者さんの主治医である場合、日々の体調変化や基礎疾患の管理状況をリハビリ担当者と密に共有できるため、より安全で効果的なリハビリ計画を立てやすいという大きな利点があります。
- 家族がリハビリに立ち会う必要はありますか?
-
毎回必ず立ち会う必要はありませんが、可能な範囲で時々同席いただくことには多くのメリットがあります。
リハビリの様子を見ることで、患者さんご本人が「できること」と「難しいこと」を客観的に理解できます。
また、リハビリ担当者から、安全な介助のコツや、ご自宅でご家族がサポートできる簡単な運動(自主トレーニング)の指導を直接受けることができます。
ご家族が感じている介護上の不安や疑問を、専門職にその場で相談し、解消する良い機会にもなります。
- 体調が悪い日もリハビリは行うべきですか?
-
無理して行うべきではありません。
特に、普段より熱が高い、血圧が極端に高い(または低い)、強い痛みや倦怠感がある、呼吸が苦しいといった症状がある場合は、リハビリを休むか、内容をごく軽いもの(安楽な姿勢の調整など)に変更する必要があります。
訪問リハビリ担当者は、訪問時にまず患者さんの体調を確認します。
もし「いつもと違う」と感じた場合、訪問診療医と連携していれば、すぐに電話で医師に報告し、指示を仰ぎます。
医師の判断でその日のリハビリを中止し、診察に切り替えることもあります。自己判断せず、専門職の判断を仰ぐことが、安全な在宅リハビリにつながります。
今回の内容が皆様のお役に立ちますように。
訪問入浴・リハビリに戻る